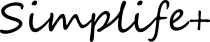昨日の機械の配置変えをしたという記事の最後に、一番の悩みであった集塵にも手を加えたと書きました。
集塵。しゅうじん。シュウジン。
塵を集める。
それが集塵機。
なのに、吸ってくれない!集めてくれない!自動かんな盤で材を削ると手前に木くずを噴き出してくる!いっちょまえに騒音を立てるのに全然吸わない集塵機なんてイヤ!!
あぁあぁ集塵に悩まされていろいろ試して、それでも改善されず、うーうー言い続けてきたこの数年。
いざ蹴りをつける時。
目次
- 1 集塵機2台体制へ
- 2 念願のバグフィルター⇒タコクロス導入!
- 3 集塵ホースはなるべく太く
- 4 その他の木工機械に関する記事
- 4.0.0.1 鉄工用ドリルから木工用ドリル(ブラッドポイント)にする方法
- 4.0.0.2 底が平らな穴を掘る!プロが絶対おすすめなフォスナービット(ボアビット・座ぐりドリル)を教えます。
- 4.0.0.3 これはすごい!横切り盤のメンテナンスで潤滑剤「ベルハンマー」を使ったら、見違えるほどスムーズになりました!
- 4.0.0.4 昇降盤のアライメント調整を行いました。
- 4.0.0.5 手順を図解で徹底解説!これが基本の自動かんな盤の調整方法
- 4.0.0.6 横切り盤のメンテナンス:定盤を外して、丸鋸の昇降時のガクンガクンとなるのを直しました。
- 4.0.0.7 昇降盤、横切り盤のVベルトをFenner Drivesのリンクベルト(Power Twist Plus)に交換しました。
集塵機2台体制へ
もともと5馬力か7.5馬力の大型のバグフィルター型の集塵機を導入しようか本気で悩んでいたころ、ある機械屋さんが、工房に機械もそんなにあるわけじゃないし3馬力の汎用集塵機を複数にした方が効率的だよ、と教えてくれました。例えば、丸鋸盤を1台動かすのにも、巨大な集塵機を起動しなければいけないってことになるよりは、小型の汎用集塵機を機械のそばに置いて、それで対応した方がずっといい、と。
フムフムそれはそうだ。
ってことで、手押しかんな盤と自動かんな盤の2台とそれ以外の昇降盤、横切り盤などの丸鋸系の機械用とに集塵機を分けるため、1台汎用集塵機を買い足しました。
念願のバグフィルター⇒タコクロス導入!
そして、さらに手を打ちました。汎用の集塵機は上袋、下袋を取り付け、吸いこんだ空気を上袋から逃がし、一緒に吸い込まれたおがくずが下袋に溜まるという仕組みです。その上袋をバグフィルター仕様に変更できるやつがあるんです。
それが「タコクロス」!
詳細はこちらにあります。⇒玉置機械商会
(ちなみに僕は機械屋さんに直接頼んで取り付けまでしてもらいました)
これの鉋くず用と鋸くず用のものを取り付けてもらいました。鋸くずは一つの屑が大きいので粗い目の上袋になってました。そして袋の数は4つに分かれています。この袋の数が分かれるほど空気を吐き出す面積が大きくなり、かつ目が粗ければ、その分空気も逃げやすく逃げる空気の量も多くなり、つまりは集塵力もあがるというものです(最初の写真の左側)。鋸くず用は、ほぼ粉上のおがくずになるので、かなり目の細かい上袋になります。上袋は7分割されたものです(最初の写真の右側)。
どちらも2倍以上は吸うようになるとの触込みでしたが、
このタコクロスが効果てきめん!
めちゃんこ吸う! 吸う!吸う!吸う!
びっくりしました。
そして、タコクロスに変えたことで、おまけとして透明のビニール袋を取り付けれるようになります。すると、いままでおがくずの溜まり具合は目でみえなかったのが、すぐわかるようになりました。そしてもっと面白いのが、この透明のビニール袋のおかげで、おがくずがサイクロン状におがくずが溜まっていく様子がわかるってことです。ぐるぐる回りながらおがくずが溜まっていく様はなかなかおもしろいですよ。
集塵ホースはなるべく太く
これまで集塵機は買った時についていた分岐管を利用していました。でもそれを使うと、Φ150をいきなりΦ100に3分割するような作りなんですね。でも集塵というのは風圧よりも風量が大事なんです。つまり太い方がたくさんの空気が通るのでよく吸います。大事なことなので、もう一度。集塵というのは風圧よりも風量が大事なんです。Φ150をいきなりΦ100に変えてしまうと風の勢いは上がるかもしれないけど、風の量は減るので全く意味がない。
ですので今回は、なるべく機械の近くまでΦ150で持って行き、そこから2台分のΦ125に分岐させるようにしました。そのためにはト管やY管などは作ってもらいました。
これもほんとにやってよかったです。
さぁ、とりあえずは頭上にホースをあげるようにしています。
目指すはスパイラルダクトで配管した工場です。気が向いたらやりましょう。
その他の木工機械に関する記事
-

-
鉄工用ドリルから木工用ドリル(ブラッドポイント)にする方法
こんにちは。 先日Twitterで鉄工用ドリルを木工用ドリル(ブラッドポイント)にする方法を知りたい人はリツイート・いい ...
-

-
底が平らな穴を掘る!プロが絶対おすすめなフォスナービット(ボアビット・座ぐりドリル)を教えます。
木工をしていると、穴の底面が平らな穴をあけることは多々あります。特に扉関係では、スライド丁番を取り付ける時は丸い穴を開け ...
-

-
これはすごい!横切り盤のメンテナンスで潤滑剤「ベルハンマー」を使ったら、見違えるほどスムーズになりました!
毎月、機械メンテナンスの日を設けて、刃物交換や注油などをしているわけですが、時折(気合が入ったタイミングで)気になってい ...
-

-
昇降盤のアライメント調整を行いました。
工房の機械について以前から気になっていたことの一つに昇降盤のアライメントが狂っていることがありました。鋸刃とトンボ定規の ...
-

-
手順を図解で徹底解説!これが基本の自動かんな盤の調整方法
木工に必ず必要となる機械がかんな盤です。特に手押しかんな盤、自動一面かんな盤はどんな工房でも無いと仕事ができません。 そ ...
-

-
横切り盤のメンテナンス:定盤を外して、丸鋸の昇降時のガクンガクンとなるのを直しました。
ここ数か月ずっときになっていた現象。それは横切り盤の鋸刃の昇降が尋常じゃないくらいに固いこと。最近は特にハンドルを両手で ...
-

-
昇降盤、横切り盤のVベルトをFenner Drivesのリンクベルト(Power Twist Plus)に交換しました。
以前からやりたかった昇降盤、横切り盤のVベルトの交換。さまざまな木工家の方が機械のVベルトをリンクベルトと呼ばれるものに ...