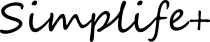木工で一つの作品を作り上げる工程の中で一番手のかかる部分はサンディングだと思っています。それまでの工程の中で積みあがってきたさまざまなナイフマークや傷やへこみなどすべてこのサンディング工程で修正しながら、ペーパーの番手を上げながら滑らかな肌触りを実現していきます。すべての工程で丁寧に部材を扱わないと、このサンディング工程で痛い目にあいます。なんとか、このサンディングを楽にできないか、とずっと悩んでいました。
このサンディングのために、オービタルサンダーやランダムアクションサンダーなどの電動工具は持っていますが、これも時間がかかります。かといって中規模、大規模の工房にあるようなワイドベルトサンダーと呼ばれる機械を何十万、何百万という投資をして導入するほどでもありません。そこで選択肢としてあがったのが、ドラムサンダーでした。いろいろな検討をしたうえで、最終的にJETのドラムサンダー 16-32を購入しました。
目次
- 1 サンディングの機械化はとてつもない効率アップになります。
- 2 ドラムサンダーを組み立てました。
- 3 調整はとてもシビア!
- 4 ベルトコンベヤーとサンディングドラムのスイッチはそれぞれ別です。
- 5 厚みのメモリはあくまでも目安
- 6 活躍を期待しています。
- 7 その他の木工機械に関する記事
- 7.0.0.1 手順を図解で徹底解説!これが基本の自動かんな盤の調整方法
- 7.0.0.2 鉄工用ドリルから木工用ドリル(ブラッドポイント)にする方法
- 7.0.0.3 底が平らな穴を掘る!プロが絶対おすすめなフォスナービット(ボアビット・座ぐりドリル)を教えます。
- 7.0.0.4 これはすごい!横切り盤のメンテナンスで潤滑剤「ベルハンマー」を使ったら、見違えるほどスムーズになりました!
- 7.0.0.5 昇降盤のアライメント調整を行いました。
- 7.0.0.6 木工集塵機をバグフィルター仕様に集塵力 大幅UP!タコクロスにしたらほんとにすごい吸うようになりました!
- 7.0.0.7 横切り盤のメンテナンス:定盤を外して、丸鋸の昇降時のガクンガクンとなるのを直しました。
- 7.0.0.8 昇降盤、横切り盤のVベルトをFenner Drivesのリンクベルト(Power Twist Plus)に交換しました。
サンディングの機械化はとてつもない効率アップになります。
かつて森林たくみ塾で木工を学んでいた時、そこにはワイドベルトサンダーという機械がありました。それで下地調整を2段階で済ませ、あとは手磨きで最後の仕上げをします。それが当たり前だと思っていましたが、自分の工房を持つにあたって、ワイドベルトサンダーはさすがに余裕がなく購入できませんでした。電動工具はオービタルサンダーやランダムアクションサンダーなどそろえてこれまでやってきましたが、やはりサンディングに時間がかかりすぎる。
たとえば、パーティションハンガーラックというのを作りましたが、これ一本一本オービタルサンダーでやるのは逆に面倒なので、結局手磨きでサンディングします。すると1本当たり7-8分せっせと磨くわけです。それが最低でも10本あるわけですよね。軽く1時間以上かけてせっせと磨くわけですよ。体力もかなり要ります。しかし、機械でやるとすると、一度に数本処理できるので、サンディング時間が1/5ぐらい短縮できます。それはそれは大きいですよ。
機械でのサンディングによって下地調整をすることによる効率的なやりかたを知っているからこそ、”知ってしまってる”からこそ、このサンディングの機械化がずっと頭にありました。だからこそ念願のドラムサンダー購入なのです。
ドラムサンダーを組み立てました。

今回、本体だけでなく、延長テーブルも併せて買い、さらに専用集塵機として、「KERV 1HP 集じん機 DC-90R2」も購入しました。これらすべてキットで届くので2時間ほどかけて組み立てました。
集塵機は組み立ててみたらとっても小さくてかわいい。こいつは、持ち運びも楽なので、旋盤やボール盤などこれまで集塵してこなかったやつにも使いまわしができるという思いで購入したので、活躍の場は広がりそうです。しかも意外に集塵力があってビックリでした。1馬力も捨てたもんじゃない。
これらの組み立ては説明書でしっかり説明してあるので、難なく終わりました。
調整はとてもシビア!

ドラムサンダーは片持ち構造です。そのため、開放側が下がってくるんじゃないか、という不安がありました。それはアメリカAmazonのこの商品のページのレビューに調整ができるという情報があったので不安は払しょくされたわけですが、それがどういう調整なのかはわかりませんでした。
で、いざ自分が組み立てて、最初のテストをしたところ、上の写真のように右側と左(開放)側では0.2mmの差がありました。開放側が下がっていたんです。
よし、さっそく調整しよう、ということで説明書通りにやり始めたものの、これとてもシビアな調整です。

本体主軸を固定しているボルトを4本緩めて、上の写真の大きなモーターの下にあるノブを回して調整します。このノブを時計回りに回せば開放側が上がり、反時計回りに回せば開放側が下がります。しかし、その回す量というのが難しい。何気なくふいっと回してやったら、まったく崩れてしまい、1mm以上の差が。。。
結局何度もテストを繰り返し、ほぼ同じ厚みで研磨できるようになりました。
コツは、開放側を下げておいて、少しずつ上げていくといいと思います。ネジを時計回りに締めていく方向で調整するのでがたつきません。

ちなみに、ドラム部分の蓋はプラスチックでできていて、それ以外は鉄です。片持ちという機構上すこしでも軽くするためなんでしょうか。でも、モーター部の重さも半端なく重いです。バランスとれていればいいんですけどね。そうすると主軸部分が、特にローラーを上下させるネジ部分がどれくらい持つのか、ちょっとそこは心配です。
ベルトコンベヤーとサンディングドラムのスイッチはそれぞれ別です。

ベルトコンベヤーとサンディングドラムは別々にスイッチになっています。ベルトコンベヤーはダイヤルで、サンディングドラムは黄色赤色のスイッチでON/OFFします。集塵機もあるので、始動、停止はそれぞれ3つのスイッチを入り・切りしなければいけません。

サンディングドラムのモーターのコードは、ベルトコンベヤーのコントローラにつなぐので、連動するのかな、と思ったのですがね。ベルトコンベヤーはスピードコントローラーを回さないと動かないし、スピードコントローラーをOFFにしないと止まりませんでした。
厚みのメモリはあくまでも目安

この機械では0.2mm~0.4mm程度のサンディングをするものですが、メモリの単位が0.5mm。しかもその指針は自分で合わせるものなので、まったくあてになりません。あくまでも目安でしかないですね。

ちなみに、この指針は最初本体の内側に入っていて、ボルトを緩めてメモリがある方へ出し、任意のところで固定するんですが、このボルトどうやって回せばいいんですか???(笑)本体内部なので、スパナが入らない、入っても回せない、、、でかなりこのボルトを緩めるのに苦労しました。たぶん、組み立てる前にやっておくべきことだと思います。組み立てた後だとスパナを回すほどのスペースもなく大変です。説明書には、そのように書いてないので。。。
活躍を期待しています。

ということで、ドラムサンダーをどんどん活用していきたいと思います。
その他の木工機械に関する記事
-

-
手順を図解で徹底解説!これが基本の自動かんな盤の調整方法
木工に必ず必要となる機械がかんな盤です。特に手押しかんな盤、自動一面かんな盤はどんな工房でも無いと仕事ができません。 そ ...
-

-
鉄工用ドリルから木工用ドリル(ブラッドポイント)にする方法
こんにちは。 先日Twitterで鉄工用ドリルを木工用ドリル(ブラッドポイント)にする方法を知りたい人はリツイート・いい ...
-

-
底が平らな穴を掘る!プロが絶対おすすめなフォスナービット(ボアビット・座ぐりドリル)を教えます。
木工をしていると、穴の底面が平らな穴をあけることは多々あります。特に扉関係では、スライド丁番を取り付ける時は丸い穴を開け ...
-

-
これはすごい!横切り盤のメンテナンスで潤滑剤「ベルハンマー」を使ったら、見違えるほどスムーズになりました!
毎月、機械メンテナンスの日を設けて、刃物交換や注油などをしているわけですが、時折(気合が入ったタイミングで)気になってい ...
-

-
昇降盤のアライメント調整を行いました。
工房の機械について以前から気になっていたことの一つに昇降盤のアライメントが狂っていることがありました。鋸刃とトンボ定規の ...
-

-
木工集塵機をバグフィルター仕様に集塵力 大幅UP!タコクロスにしたらほんとにすごい吸うようになりました!
昨日の機械の配置変えをしたという記事の最後に、一番の悩みであった集塵にも手を加えたと書きました。 集塵。しゅうじん。シュ ...
-

-
横切り盤のメンテナンス:定盤を外して、丸鋸の昇降時のガクンガクンとなるのを直しました。
ここ数か月ずっときになっていた現象。それは横切り盤の鋸刃の昇降が尋常じゃないくらいに固いこと。最近は特にハンドルを両手で ...
-

-
昇降盤、横切り盤のVベルトをFenner Drivesのリンクベルト(Power Twist Plus)に交換しました。
以前からやりたかった昇降盤、横切り盤のVベルトの交換。さまざまな木工家の方が機械のVベルトをリンクベルトと呼ばれるものに ...